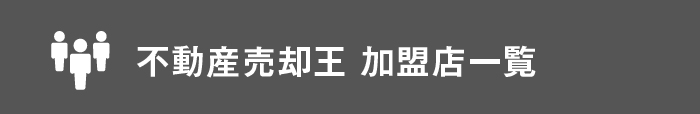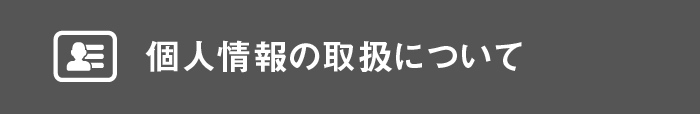序章:朽ちゆく村の声
「また今年も何も変わらないな……」
里山の静けさを破るように、鳥の声とともにおじいさんが呟いた。彼が暮らす村の奥には、人の手が入らなくなった空き地が広がっている。雑草は人の背丈を超え、朽ちた家々が静かに風雨に晒されていた。

ここは、かつて大家族でにぎわった場所。しかし子どもたちは都会に出て行き、誰も戻らなくなった。相続登記がなされず、今では誰がこの土地を管理するべきなのかも分からない。村ではこのような「所有者不明土地」が増え続けていた。
転機:大震災が呼び覚ました記憶
そんな問題が全国的に注目されたのは、2011年の東日本大震災がきっかけだった。
「復興したいのに、土地の所有者が分からない……」
被災地で困り果てた自治体職員の声がニュースで報じられた。登記簿を調べると、明治時代の名前が所有者として記されており、交渉すらままならない状況だったという。この事実は、村のおじいさんのような地方の住人だけでなく、都会に住む人々にも大きな衝撃を与えた。
法整備という希望の光
その後、政府は本腰を入れて法整備を進めた。2020年には土地基本法が改正され、土地所有者に管理責任を持たせる規定が設けられた。さらに、2023年4月には「所有者不明土地・建物の管理制度」が施行され、所有者が不明でも裁判所の許可を得れば、管理人が土地を売却処分できるようになった。
また、相続登記の義務化も始まった。これにより、相続が発生した場合、3年以内に登記を行わないと過料が科される。おじいさんの村でも、この新しい制度を使って荒れ地の一部が自治体に引き取られ、公園として整備されることが決まった。
現実の壁:能登半島地震の教訓
しかし、現実はそう簡単ではなかった。2024年1月に発生した能登半島地震では、倒壊した建物の撤去が所有者不明のために遅れ、多くの課題が浮き彫りになった。解体するには所有者全員の同意が必要であり、行方不明の相続人を探す手間が膨大だった。
「これだけの法整備があっても、まだ時間がかかるんだな……」
おじいさんもこのニュースを見て、自分の村の未来を思わず重ねた。
未来への課題:土地をどう活かすか
「でも、希望がないわけじゃない。」
相続土地国庫帰属制度によって、国が土地を引き取る仕組みも利用が進んでいる。これにより、管理が難しい土地を手放す道が広がったのだ。おじいさんの隣家でも、相続人が東京で暮らしており管理が困難な土地を、国に引き取ってもらうことができた。
「その土地が公園になれば、孫たちが遊びに来るとき、喜んでくれるかもしれないな……」
おじいさんはそう思いながら、孫が笑顔で走り回る未来を夢見た。
終章:土地が繋ぐ新しい未来
荒れた土地も、適切な制度と人々の協力があれば、新しい命を吹き込むことができる。忘れ去られた土地は、ただの空き地ではなく、人と人を繋ぎ、未来を切り開く鍵となるのだ。
おじいさんは、自分が見守り続けてきた土地が新しい形で活用されることを期待しながら、孫たちの訪れる日を楽しみに待つのだった。